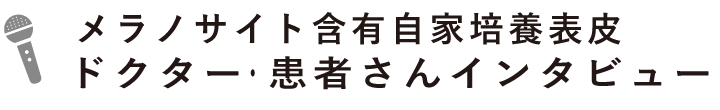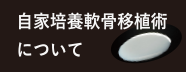-

-

-
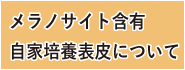
-

-

-
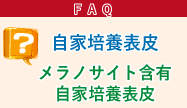
-
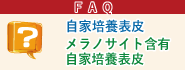
-

治療について
-
メラノサイト含有自家培養表皮
白斑の治療
白斑とは
白斑治療例
白斑についてFAQ
鳥山先生インタビュー
-
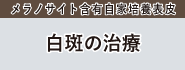
-
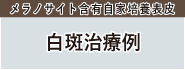
-
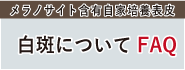
-
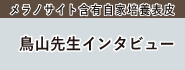
-
自家培養表皮
熱傷の治療
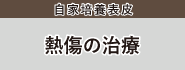
-
自家培養表皮
母斑の治療
林先生インタビュー
森本先生インタビュー
患者さん・ドクター インタビュー
-
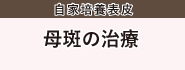
-
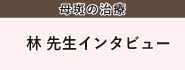
-
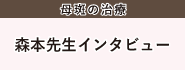
-
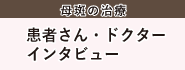
-
自家培養表皮
表皮水疱症の治療
患者さん・ドクター インタビュー
-
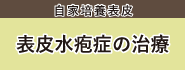
-
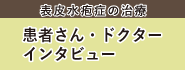
-
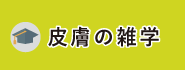
皮膚の再生医療
が受けられる病院-
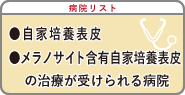
-
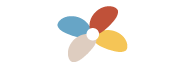
-
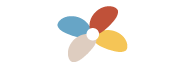
-
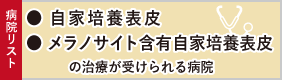
こちらもぜひご覧ください
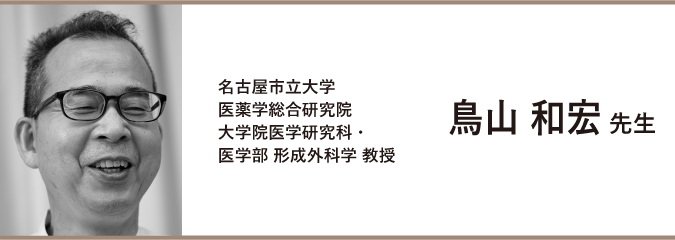
「白斑治療」についてお聞きしました
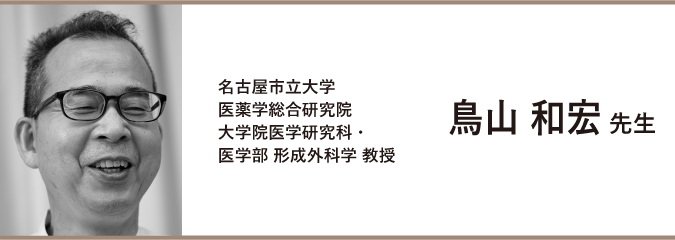
「白斑治療」についてお聞きしました
- 本日はお忙しいところありがとうございます。初めに名古屋市立大学に白斑治療に来る患者さんについてお教えください。
- 当院には年間100名以上の白斑の患者さんが来院されています。 男女比は半々より少し女性が多いようです。年齢も幅広く、小学生、中高校生から70代80代の方もいらっしゃいます。 高齢の患者さんは、長い間ずっと気にされてきて、やっぱり治したいと決心されて来られるようです。 全体をみると若い方が多いですね。また、遠方から来られる患者さんも多いです。 東京、横浜、福岡、佐賀、福井など全国からお見えになります。 そういった患者さんは、かかりつけ病院からの紹介やご自分でしっかり調べて当院へ来てくださいます。
- 白斑にはいくつか種類がありますが、それについて教えてください。
-
 白斑には生まれつきある「先天性」と生まれた後で発生する「後天性」があります。
一番多いのは後天性の「尋常性白斑」です。白斑の約60%を占めます。その「尋常性白斑」は大きく3つに分かれます。
ひとつは「汎発型」といい、全身に白斑ができてくるもので、特に肘や膝などの擦れる場所に多いです。
次に「分節型」で、神経の走行に沿って出てきます。3つめに「限局型」で、汎発型と分節型に分類されないものです。
また、化学物質による白斑もあります。今から10年ほど前、ロドデンドロールを含む薬用化粧品使用後の白斑が社会問題になりました。
白斑には生まれつきある「先天性」と生まれた後で発生する「後天性」があります。
一番多いのは後天性の「尋常性白斑」です。白斑の約60%を占めます。その「尋常性白斑」は大きく3つに分かれます。
ひとつは「汎発型」といい、全身に白斑ができてくるもので、特に肘や膝などの擦れる場所に多いです。
次に「分節型」で、神経の走行に沿って出てきます。3つめに「限局型」で、汎発型と分節型に分類されないものです。
また、化学物質による白斑もあります。今から10年ほど前、ロドデンドロールを含む薬用化粧品使用後の白斑が社会問題になりました。
- 白斑になると具体的にはどうなりますか。
- 白斑は皮膚の色素が抜けて、皮膚が白くまだらになる以外、体調などの変化はありません。 ただ、白斑になる方は、甲状腺機能異常やアトピー性皮膚炎、円形脱毛症、乾癬などの合併症がある方も多いので、そちらの症状にも気をつけなければなりません。 白斑は、見た目以外は身体のデメリットはありませんが、その見た目で患者さんのQOL(生活の質)が下がります。 そのため、治療以外でも服装やカモフラージュ(メイク)といった方法で隠すことも少なくありません。
- 白斑治療の流れと治療方法について具体的に教えて頂けますか。
-
まず皮膚科を受診していただき、白斑の型や進行の具合、いつからどれくらいの期間発生しているか、これまで受けてきた治療などの詳細を医師が確認します。
尋常性白斑なのか、他の白斑なのかが最初の重要な判断になります。
尋常性白斑であれば、次にダーモカメラ(肉眼では判断が難しい皮膚病変の観察や診断を補助するカメラ)で拡大して、その白斑が今どのような状態であるのかを確認します。
はじまったばかりの白斑なのか、これから大きくなっていくのか、進行がとまっているのか等の診断になります。
先ほど申し上げた合併症についてもしっかり確認し、それから治療が始まります。
「尋常性白斑に関するガイドライン」
に基本的な治療方針が示されています。
最初は、塗り薬が処方されます。副腎皮質ステロイド外用剤、活性型ビタミンD3外用剤、タクロリムス軟膏などです。 白斑が限られた場所にある「限局型」には反応がみられることが多いです。 それで効果がないようでしたら、光線療法とよばれるナローバンドUVB、エキシマレーザー、エキシマライトなどを使った治療を行います。 塗り薬と併用する場合も多くありますね。こちらは全身に白斑が広がっている「汎発型」に反応がみられることが多いです。 エキシマレーザーはピンポイントで患部に紫外線を当てられるのですが、器械が高額であり、この治療が行えるところはまだ少ないです。 エキシマライトは、それより広範囲に照射するもので割と一般的だと思います。塗り薬もJAK阻害剤(2025年9月末時点では白斑については保険適用なし)など新しいものが開発されて出てきています。
 そして、どの治療法も3カ月から6カ月毎に治療効果を評価し、患者さんともよく話し合い、その後の治療を進めます。
尋常性白斑の場合には、治療が終わってからも再発することがありますので注意が必要で、治癒後も少なくとも半年は治療を続けています。
これらの治療で効果が得られない場合は、外科的な治療(手術)が検討されていきます。
私たち医師と患者さんにとって、とても画期的な治療が行えるようになったと思います。
そして、どの治療法も3カ月から6カ月毎に治療効果を評価し、患者さんともよく話し合い、その後の治療を進めます。
尋常性白斑の場合には、治療が終わってからも再発することがありますので注意が必要で、治癒後も少なくとも半年は治療を続けています。
これらの治療で効果が得られない場合は、外科的な治療(手術)が検討されていきます。
私たち医師と患者さんにとって、とても画期的な治療が行えるようになったと思います。
- 光線療法などで効果がでない場合もあるということですが、その後は皮膚移植になるのでしょうか。
-
ステロイドの塗り薬は長く使用すると副作用も出てきます。
そのため免疫抑制剤や活性型ビタミンD3の塗り薬に変えていくこともあります。
光線療法もエキシマライトで効果がなければ、エキシマレーザーの治療に変えることもあります。
それでも効果がみられない状態が1年以上続く白斑の場合には、手術(皮膚移植)が選択肢となります。
手術方法はいくつかありますが、大きく分けると、ひとつは皮膚の組織を持ってくる方法、もうひとつは細胞単位で持ってくる方法になります。
皮膚の組織を持ってくる方法は広い範囲の皮膚をとらなくてはならず、治療できる範囲が限られます。
「ミニグラフト」という方法が、皮膚の組織をもってくる方法の代表です。円柱状にくり抜いた健常な皮膚を白斑の部位に移植します。
最近では技術が進化していて、直径1ミリ以下という小さな皮膚を移植することが可能です。
移植された皮膚のメラノサイト(色素細胞)がじわじわ広がり、周りに拡張していきます。課題としては均一に色が着かずに敷石状になってしまうことがあります。
「吸引水疱蓋表皮移植」も多く実施されている方法で、患者さんの健常な皮膚を注射筒(シリンジ)で吸引して水ぶくれを作り、その皮膚を切り取って患部に移植するという方法です。 また、最近では「自家細胞懸濁液」という、患者さんの健常皮膚片から、表皮細胞や色素細胞、線維芽細胞など、皮膚の構造に重要な細胞を分離し、自家細胞懸濁液を作って移植する方法も出来てきました。 そして再生医療の「メラノサイト含有自家培養表皮」があります。患者さんの健常皮膚から採取した皮膚(表皮)を培養して8×10㎝のシートを作って移植します。 どの手術もなくなってしまったメラノサイトを補充する目的で行います。 - メラノサイト含有自家培養表皮を用いた新しい治療について教えてください。鳥山先生はこの治療方法に初期の頃(2017年7月)から関わっていらっしゃいますが、この辺りも含めてお聞かせください。
-
 「メラノサイト含有自家培養表皮」を使った白斑治療は、2024年10月から保険がきく再生医療となり注目されています。
実は当院では保険がきくようになる前から、自由診療で皮膚科と連携して、この治療法を実施してきました。
日本は外国と比べて「再生医療」が進んでいて、国が認可した製品が多くあります(2025年8月末時点で21品目)。
更に、国がまだ認可していない製品であっても、医師と患者さんと合意の上、自由診療で行える場合があります。
当院ではメラノサイト含有自家培養表皮を自由診療で37例に移植し、保険で治療した症例とあわせて44例ほど治療しています。
「メラノサイト含有自家培養表皮」を使った白斑治療は、2024年10月から保険がきく再生医療となり注目されています。
実は当院では保険がきくようになる前から、自由診療で皮膚科と連携して、この治療法を実施してきました。
日本は外国と比べて「再生医療」が進んでいて、国が認可した製品が多くあります(2025年8月末時点で21品目)。
更に、国がまだ認可していない製品であっても、医師と患者さんと合意の上、自由診療で行える場合があります。
当院ではメラノサイト含有自家培養表皮を自由診療で37例に移植し、保険で治療した症例とあわせて44例ほど治療しています。
この治療法に関わるようになったのは、「メラノサイト含有自家培養表皮」の前に開発された「自家培養表皮」と関りがあったためです。 自家培養表皮についても当初から製造販売会社であるJ-TECさんと、さまざまなディスカッションを交わせていただきました。 というのも、当初は自家培養表皮を研究室で手作りしていたのです。 手作りしていた自家培養表皮は、穴があいたり、色が付かなかったりと試行錯誤しましたが、J-TECさんの開発により製品化され、全国で使えるような環境になったことは画期的だと思います。 自家培養表皮は当初、熱傷の患者さん向けに開発されましたが、先天性巨大色素性母斑、表皮水疱症の治療にも使用できるようになりました。 開発当初は再生医療の法律がきちんと整備されていない時代でしたので、途中で開発に待ったがかかったりもして大変だったです。 当院でも自家培養表皮を巨大色素性母斑の症例で使用しています。母斑を削った後に自家培養表皮を移植すると、速やかに傷が治りますので瘢痕になりにくいです。 新たに発売されたメラノサイト含有自家培養表皮は白斑用ですから、白斑の患者さんに使いますが、こちらの良いところはやはり、患部のサイズを余り気にしないで移植が行えることでしょうか。 健常な皮膚をとる面積が小さいため患者さんの負担が少なく広い面積の白斑をカバーすることができます。また、均一な色素再生が期待できることもメリットです。 一方で、5週間の培養期間が必要となること、高額医療となる点が注意点ですね。 高額医療については、患者さんの負担を最小限に抑える 高額療養費度 がありますので安心できると思います。
(次ページにつづく)